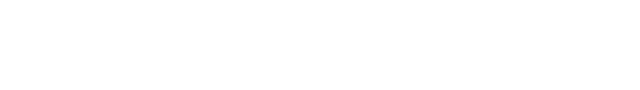だるさ(倦怠感)
だるさ(倦怠感)とは
最近疲れがなかなか取れない、朝起きたときにだるさを強く感じる、または午後から夕方にかけて疲れがひどくなるなど、そういった症状はないでしょうか。
厚生労働省が発表した令和4年国民生活基礎調査の結果では、だるさ(倦怠感)の有訴者数は人口千人あたり36.7人であり、頭痛や目のかすみと同じ程度、だるさを感じている方がいます。
日本国民の約450万人がだるさを認めており、多くの方がだるさで悩まれています。
だるさ(倦怠感)の原因となる病気
だるさは全身倦怠感を指すことが多いのですが、だるいという言葉は様々な症状を含んでいます。
例えば、息切れがする、眠れない、筋力の低下などの症状を、患者さんは「だるい」と訴えてクリニックを受診することがあります。
そのため、「だるい」という訴えで受診された場合、具体的な症状を確認することが大事です。
例えば、下記のような症状の有無、経過を質問することがあります
- 眠れていない
- 息切れ
- 筋力が低下している
- 気分の落ち込みが続いている
- 休んでも疲れが取れない
- 発熱や体重減少がある
- ふらつく
- 職場や家庭でストレスを抱えている
- ここ最近急に疲れが出てきた
- 長い間、半年以上だるさが続いている
だるさ(倦怠感)を引き起こす病気は多岐にわたりますが、上記の症状を踏まえ下記の原因の有無を精査していきます。
感染症
ウイルスや細菌感染で倦怠感は引き起こされます。肺炎や心内膜炎・心筋炎、急性肝炎、結核などがあります。
また、インフルエンザやCOVID-19感染後に疲労状態が続くことがあり、約1か月疲れが長引くことがあります。
糖尿病
糖尿病の中でも、急激に症状が悪化する劇症1型糖尿病の場合、だるさが初期症状として出現します。
貧血
貧血で疲労感を訴えることがあり、特に月経のある女性では鉄欠乏性貧血の頻度が高いです。
内分泌疾患
甲状腺の機能が亢進または低下、副腎機能が低下した際にも倦怠感を認めることがあります。
悪性疾患
だるさだけで判断することは難しく、局所の身体症状を伴っている場合(例:疼痛や出血など)に考慮されます。
体重減少や発熱が続いている場合などは除外できないため、精査が必要です。
神経・筋疾患
筋力低下ではなく、倦怠感が症状として強く認めることがあります。
筋力低下の日内変動や、話しづらさ、飲み込みにくさなどを確認します。
重症筋無力症やALS(筋萎縮性側索硬化症)、多発性硬化症だけではなく、認知症でも倦怠感を認めることがあります。
うつ病
精神的なストレスはだるさと関係しています。この1か月で気分の落ち込みやふさぎこむことがある、物事に対する興味を失い楽しくなくなった、ということがあればうつ病の可能性があります。
薬剤性
薬が原因でだるさを認めることがあります。例えば、睡眠薬や抗うつ薬、降圧薬、抗ヒスタミン薬、オピオイド等で倦怠感が引き起こされます。
アルコール
過度な飲酒後や、飲酒をしていない時に症状を認める(離脱症状)ことがあります。
心肺機能や腎機能の低下
肺気腫(COPD)や肺結核などの肺疾患、心不全や虚血性心疾患、腎不全でも倦怠感を認めます。
だるさ(倦怠感)の検査と診断、治療
血液検査(貧血の有無、電解質、甲状腺機能、糖尿病の有無など)、尿検査、胸部レントゲン、心電図などを行い、原因を精査します。
必要に応じて、CT検査を追加することがあります。
だるさ(倦怠感)の原因は様々であり、原因疾患に応じて治療を行っていきます。